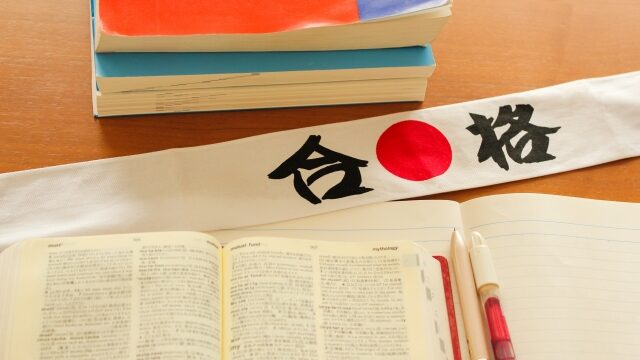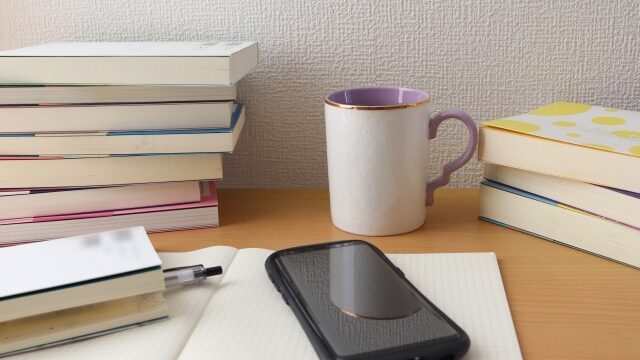大学受験に英検の資格を使った制度が導入されました!
スコアや級によって免除されたり、加算されたりする制度です。
これから、各大学で積極的に導入が検討されていくでしょう。
少しでも有利な状態で臨みたいと思いませんか?
そこで、英検について基本的なことから受験に必要な点数までを紹介します。
少しでも参考になっていただけたら嬉しいです。
では、早速いきましょう!
大学受験で英検を受ける際の受験級とレベルについて
大学入試で英語のスコアが合否に関わる制度が登場し、英語に関する資格試験を受験する生徒が増えています。
その中でも代表的な資格である「英語検定」については、以下の合格を目指すのがいいと言われています。
- 準一級
- 2級A
ひとつずつ解説していきますね。
準1級を合格できれば理想
準1級は、レベルで言うと大学中級程度のレベルです。
つまり、高校生で大学の中級レベルの知識をつけなければならないことになります。
それに伴って、準1級の資格を持っていれば、いわゆる難関大学と呼ばれる受験校にメリットがあります。
準1級を持っている受験生の割合はかなり低い分、英語の評価はとても高くなります。
難易度は高いため、まずは2級を目標に勉強してみてはいかがですか?
まずは2級A合格を目指そう
まずは、「2級A合格」を目指しましょう!
「2級A」とは、英検2級に合格して、4技能合計CSEスコアが2150点以上に与えられる資格のことです。
つまり、2級を取得してそこで終わらずに、その先に一定の条件をクリアすると取得できる資格なのです。
CSEスコアに関してはこの後で詳しく解説します。
なお、「英検2級合格」だけでももちろん評価の対象になります。
しかし、「英検2級合格」よりも「英検2級A合格」のほうが狭き門であるため、より評価は高いです。
英検利用をしている国立大学はある?
2021年の入試では、全国立大学82大学中、50大学が英語の試験利用をしています。
なんと、半数以上の大学が利用しているのです!
国立大学でも積極的に取り入れている大学は多くなっています。
英語の資格を利用して大学受験に臨む時が当たり前になってきているんですね。
大学受験のための英検はいつまでに何級を受けるべき?
高校3年生の夏休みまでに、理想は準1級を一般的には2級を取得しましょう!
準1級の資格を持っていると多くの大学で高評価を得ることができます。
しかし、それに伴って難易度は高いです。
英検は6月、10月、1月頃に公開試験があり、それに合格すると1ヶ月後の7月、11月、2月に2次試験があります。
夏休み以降は受験勉強に専念してもらいたいため、高3の6月に公開試験を受験して7月に2次試験を受験するのが最後の受験になるかと思います。
この期間で取ってもいいですし、それ以前に取れる機会があれば取ってほしいです。
まずは、2級を取得することをおすすめします。
大学受験のための英検はいつまでに合格していれば間に合うのか?調査書・推薦の場合は?
英検の合格発表は、試験日の約1ヶ月後。
6月の試験までに受験して7月に合格できていれば間に合います。
推薦の受験を考えている受験生であってもこの期間で取れば間に合うでしょう。
夏休みが明けて2学期になれば進路を本格的に決定していかなければなりません。
しっかりと計画を立てて進めていきましょう!
大学受験で英検が使えないパターンはある?
使えないパターンは大きく2つあり、
- 大学側が英語の資格試験を必要としていない場合
- 大学側が課しているものの、必須の級に到達していない場合
が考えられます。
基本的に、「2級を取得していれば使える!」と思っていて大丈夫です。
念のために、志望する大学が何級の資格を課しているのか?そもそも英検の資格を取る必要があるのかはしっかりとチェックするようにしましょう!
CSEスコアの利用もアリ!CSEスコアとは?
かつての英検は、「合格か?不合格か?」の合否を判断する試験でした。
しかし、グローバル化に伴って英語力が必須となってきた現代で、合否判定だけではなく、CSE(Common Scale for English(英語のための共通尺度))と呼ばれる英語の4技能(Listening、Reading、Writing、Speaking)を評価するスコアが採用されるようになりました。
CSEスコアは、これまでの合格不合格で見るよりもより細かな視点を持つことができ、自分が4技能の中でどれが一番弱いのかもわかります。
CSEスコアの各技能(4技能)の満点スコアは以下の通りです。
- 1級 各850点 850×4技能=3400点満点 合格点:(R/L/W:2028点,S:602点)
- 準1級 各750点 750×4技能=3000点満点 合格点:(R/L/W:1792点,S:512点)
- 2級 各650点 650×4技能=2600点満点 合格点:(R/L/W:1520点,S:460点)
- 準2級 各600点 600×4技能=2400点満点 合格点:(R/L/W:1322点,S:406点)
- 3級 各550点 550×4技能=2200点満点 合格点:(R/L/W:1103点,S:353点)
合格するための正答率は、
- 1級 R/L/W:2028÷2550=約80% S:602÷850=約71%
- 準1級 R/L/W:1792÷2250=約80% S:512÷750=約68%
- 2級 R/L/W:1520÷1950=約78% S:460÷650=約70%
- 準2級 R/L/W:1322÷1800=約73% S:406÷600=約68%
- 3級 R/L/W:1103÷1650=約69% S:353÷550=約64%
となっております。
級が高いにつれて正答率も高いです。
自身が受けようとしている級をチェックしてみてください!
新方式の英検のみ大学受験に適用できる!新方式と従来型の違いとは?
英検の方式について、以下を比較しつつまとめていきます。
- 従来型英検
- 新方式型英検【CBT】
- 新方式型英検【英検S-CBT】
従来型英検
- 日程:1次試験と2次試験があり、1次試験を合格しないと2次試験へ進めません。
- 開催日:年に3回(6月、10月、1月頃)
- 対象級:5級~1級
- 回答方法:1次試験は紙で筆記試験、2次試験は面接によるスピーキングテスト
今までの試験がこの従来型のものです。
1次試験と2次試験に分かれており別日に開催されます。
1次試験では「紙での筆記試験」、2次試験では「面接によるスピーキングテスト」が行われます。
ただし、1次試験に合格しなければ2次試験に進むことができません。
受験できる級は5級~1級です。
大学受験に適用できるのは、次にまとめる「新方式英検」の方になります。
新方式型英検【CBT】
新方式には、英検CBTと英検S-CBTがあります。
- 日程:従来型の試験とは異なって、1日ですべて受験します。
- 開催日:年に3回(4~7月、8月~11月、12月~3月)
- 対象級:3級~1級
- 回答方法:出題も回答もパソコン
従来型英検と問題形式は変わりませんが、出題方法と回答方法が唯一異なります。
英検CBTでは、出題・回答が全てパソコンで行われます。
日程は全て1日で行われ、4技能全てを受験します。
新方式型英検【英検S-CBT】
- 日程:英検CBTと同じく1日ですべて受験します。
- 開催日:年に2回(4月~7月、8月~11月)
- 対象級:3級~準1級
- 回答方法:出題はパソコン、回答は紙です。
出題はパソコンで回答を紙でします。
開催期間は、年に2回です。
スピーキングはヘッドセットで吹込みによる試験です。
大学受験での英検利用の種類
実際に、英検が大学受験でどのように使われているのか紹介します。
- 英語の試験が免除される
- 英語の試験に得点換算
このパターンがほとんどです。
なお、大学によって制度は大きくことなります。
詳しくは、受験したい大学の募集要項を必ず見てくださいね。
英語の試験が免除される
大学ごとで一定の点数・級を取得することで大学入試の英語の試験が免除される場合があります。
この場合、英検の一定の点数を取得すれば、大学入試の英語の勉強をしなくてよいため負担が減ります。
英語の試験に得点換算
一定の点数・級を取得することで、大学入試の英語の試験に得点換算される場合があります。
英語の資格で一定の点数・級を取得していた場合、入試の英語の点数が悪かったとしてもそれをカバーしてくれます。
大学受験で英検利用をした場合の合否判定のされ方
合否判定のされ方は、大きく2つあります。
- 級の取得で合否を判断するやり方
- CSEスコアで判断するやり方
以下でひとつずつ説明していきます。
級に合格していればOKとする場合
求められる級に合格していればよい場合です。
基本的にこのパターンが多いかと思われます。
資格に合格すれば判断してくれるのです。
判断基準が分かりやすいため多くの大学で採用されています。
合格していなくてもスコアが足りていれば良い場合
英検2級合格とともに、CSEスコアと呼ばれるスコアも表示されます。
英検2級を合格した際には、2000以上のスコアとして出ます。
仮に英検2級に不合格して2000に近い1900点のCSEスコアを取ったとしても合格とみなされる場合があります。
資格は取得できなかったものの、スコアで合格するイメージです。
現時点では、CSEスコアよりも資格取得での合否を決めている大学が多いため、各大学のホームページなどをよく参照するようにしてください。
合格してさらにスコアも足りている必要がある場合
この場合、比較的難易度の高い大学に求められる場合ではないでしょうか?
合格してさらに一定のスコアを取らなければならないため2段階のフィルターがかかっているようなものです。
資格取得とCSEスコアの両方を求められるということで、合格のハードルは高くなります。
大学受験の英検の適用範囲は2年以内とされる【有効期限(有効期間)は学校に要確認】
英検の適用範囲は、出願からさかのぼって2年以内の成績しか使えないことが多いです。
また、有効期限を設けていない大学もいくつか存在するため、大学のホームページなどでチェックするようにしてください。
大学受験で英検利用する際に受験生が気を付けるべきこと
受験しようと考えている各大学のホームページを参照して、
- 志望大学は英検を評価してくれる大学なのか?
- 評価してくれる大学であるならば、どの程度のレベルを要求されているのか?
- 英検の利用種類を把握しているか?
これらに気を付けるようにしてください。
しっかりと把握できたのなら、英検の勉強を始めていきましょう!
まとめ
今回は、「大学受験で英検を使うこと」について紹介しました。
少しでも参考になっていただけたら嬉しいです。
大学入試でもうすでに英語の4技能を試され、より実用的な受験へとシフトしていっています。
今後は、この方式が全国の大学で当たり前になってくるかもしれません。
そのために、大学入試を迎える前に英語の資格試験を取得して少しでも有利になるよう受験を進めていってほしいです。